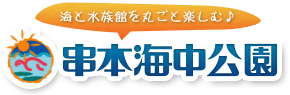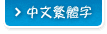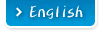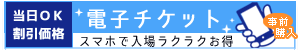スタッフブログ【さびうらびより】ひらりん一覧
スタッフブログ【さびうらびより】ひらりん一覧
スタッフブログ【さびうらびより】スタッフ:ひらりん一覧
串本の様子や様々な串本の生き物たちを、
スタッフが交代でご紹介します。
- 最新記事
- 第360回 錆浦より
- 第353回 さんごガチャふぁいなる
- 第347回 さんごガチャ中間報告
- 第342回 目目連
- 第337回 石の上にも四年
- カテゴリ
- BigWest (3)
- Go (20)
- くろすけ♀ (67)
- くろちゃん (3)
- こて (18)
- さく太郎 (16)
- しまっち (25)
- そらすずめ (9)
- とーる (69)
- ひらりん (23)
- ひろぽん (6)
- ひーちゃん (12)
- まつ (1)
- ゆーみん (18)
- クチヒゲノムラガニ (5)
- ナツメリ (7)
- ハムいち (57)
- ブログ更新 (366)
- マンジュウイシ (1)
- 海人 (6)
- 青ネギ (4)
- 月別アーカイブ
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (9)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (5)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (2)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (3)
- 2012年1月 (3)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (3)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (5)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (6)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (5)
- 2010年4月 (4)
- 2010年3月 (3)
- 2010年2月 (3)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (6)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (8)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (7)
- 2009年6月 (5)
第276回 ミノカサゴに刺されると人はどうなるのか
さかのぼること3月ほど前。
私の身にとても衝撃的な出来事が起こりました。
それは・・・
ミノカサゴに刺されちった。。
このてのブログ記事ではだいたい「みんなも注意しようねぇ~テヘペロ」的な軽い感じがお約束な気がしますが、
今回ばかりは真剣に苦しみましたので真剣に書きます。
結論から言いますと、
ミノカサゴに刺されるとハチャメチャに痛い。。
それでは、私が記録した「ミノカサゴに刺されると人はどうなるのか」をお楽しみください。
(※痛々しい画像が含まれます。。あと、おじさんの汚い手の画像が続きます。。)
・
・
・
7月某日
8:50頃
展示生物を交換する際、うっかり小さなキリンミノの入った水槽に手を入れてしまい、ほんの少しだけ背鰭の先端が右中指に刺さる。瞬時に「あ、ヤバいやつや」と察し、すぐに40℃以上のお湯に患部を浸す。
9:00頃
患部の痛みが増し、お湯に浸しておくのが困難に。「ミノカサゴ 刺された」とネットで検索するもお湯につける以外の対処法は得られず。ただ、おそらく死にはしないだろうという情報は得る(確証はありません)。
9:30頃
右手全体がパンパンに腫れ、刺された中指が汗をかき始める。この頃になると手を動かすのも困難になり、脂汗をかきながら机に座りただただ悶える。痛みを例えるなら5秒おきに大きなペンチで中指周辺を押し潰されているような感じ。
10:30頃
痛みと右手の腫れはピークに。まるで金槌で右手を打ち付けられているような痛みが続く。本気で病院行こうか迷いつつ、気を紛らわそうと意味もなく歩き回る。止まっていると筋肉が痙攣して右手全体が小刻みに震える。
11:30頃
痛みのピークは過ぎるが、依然ズキズキした鈍痛は続く。若干気力も回復し、もう病院に行かなくても大丈夫であることを確信する。
13:00頃
若干の痛みは残るがようやく回復。右手の腫れも少しずつ引き始める。
15:00頃
痛みはほぼ無くなる。刺された箇所を押さえると痛む程度に。手の腫れは依然残るがいつも通りの作業も問題なく執り行える。
翌日
刺された箇所を押さえると若干痛むものの、手の腫れも痛みもほぼ完治。
翌翌日
何故か刺された右中指のみポロポロと皮が剥ける。腫れも痛みも無し。
3週間後
完治。
刺された箇所を押さえても痛みを感じなくなる。
・
・
・
はい。
以上、私がキリンミノに刺されてからの記録となります。
あくまで私自身の主観的な記録ですので誰しも同じ症状ではないと思いますが、もし刺された場合には早めに病院へ行くことをお勧めします。
ミノカサゴの仲間って綺麗だし優雅だし見ている分には素敵だけど、あの子たち本当は超怖いから、
みんなも注意しようねぇ~テヘペロ。。。
by ひらりん
第270回 サンゴの産卵観察 in 2019
毎年恒例サンゴの産卵調査の季節がやってきました。
この時期になると修行僧のように毎晩海へ向かいます。
今年は5月19日から観察を始めました。
ミスガイのつぶらな瞳に癒やされつつ、産まない産まないと心が荒んでいく中、
7月2日、3日にようやく今年初のスギノキミドリイシの一斉産卵が観察されました。
黒潮の蛇行に伴い、水温の上がり方が緩やかだったこともあってか、例年よりもやや遅めの産卵となりました。
今年は産卵時間も遅く、23時30頃をピークに22時から24時くらいまでだらだらと産卵が続きました。
あんまりだらだらと産卵が長引くため、撮影はあきらめて帰ろうかとも思ったのですが、何とか頑張って撮影しました。
サメハダテナガダコも幻想的な光景に見入っているようでした。
因みに本当の今年初産卵はタカクキクメイシ。
6月26日に観察されました。
こちらは派手さこそありませんが一粒一粒のバンドルが大きいので迫力があります。
また、以前海水の味について書きましたが、
魚達がまいうーまいうーと食べているサンゴのバンドルは少し苦かったです。
この後はクシハダミドリイシ、エンタクミドリイシと続く予定ですので、
引き続き観察を続けます。
by ひらりん
第264回 海を味わう
こんなことを言ってしまうと初っ端からドン引きされそうですが、
他人には理解してもらえない自分だけの秘かな楽しみってありますよねー。
例えば
ペットの足の裏を嗅ぐのが好きな人。
とか
アイスクリームの蓋の裏に付いたやつを食べるのが好きな人。
とか
部屋では全裸で過ごしている人。
とか・・・
で、
私の秘かな楽しみとは
ダイビング中にこっそり海水の味見をすること。
季節や地域によって意外と味が違うんですよねー。
・・・とはいえ、私は別にグルメでもなんでもなく、
そもそも海水すら時に美味しいと感じる私の味覚が正しいはずもないのですが、
毎年この時期になるとふと思うのが、
海水が青臭くて苦い。

なぜか春濁りの時期になると海水が青臭く苦く感じます。
春濁りの主な原因は植物プランクトンの発生によるものですが、
もう一つ、この時期大量に繁茂するのがフクロノリ。

そこら中がフクロノリだらけになります。
そしてフクロノリの胞子もまた海を濁らせます。
・・・ではフクロノリがこの時期の海水に苦みと青臭さを与えているのでしょうか?
というかそもそもフクロノリって誰も採ったりしてないけど、食べられるのでしょうか?
そこで・・・
はい。拾ってきましたー。
それではいただきまーす。
・・・
シャリッ…
モグモグ…
んーー!ぺっぺッ。。
青臭い!まさにこの時期の海のあれだ!
リンゴの皮だけを食べているかのようなビミョーな食感の後にものすごい青臭さが襲ってきました。
でも・・・
苦くはないね。
ということで、
少なくともフクロノリの胞子や欠片が海水の臭みの一部になっている可能性がありますが
苦味の原因についてはよくわかりませんでした。。
一つ分かったことがあるとすれば、
フクロノリは食べなくても大丈夫だということですね。。
因みに
これまでで一番美味しかった海水は某真鯛の養殖生け簀の近く。
これでもかと濁った海水に謎の旨味を感じました。
潜水後、一緒に潜った方々にここの水、美味いですね!と言ったら、
見事にドン引きされてしまいました。。
良い子は決してマネしないように。
by ひらりん
第254回 サンゴの産卵調査 in 2018
今年も例年同様サンゴの産卵調査を行っています。
サンゴの産卵は基本的に夜間に行われるので21時頃から潜水を行います。
日頃から潜り慣れているポイントとはいえ真っ暗な海に単身繰り出すのはいろんな意味で結構怖いですが、
昼間あまり見かけることのない生物に出会うとチョットテンションが上がります。
たとえば
エイラクブカが近寄ってきたり
寝ぼけたセミホウボウに接近できたり
全身真っ黒なタツナミガイに遭遇したり
そのほかにも色々な生き物たちに出会うことができます。
そんなこんなで、7月13日にようやく今年最初のサンゴの一斉産卵が確認できました。
産卵したのはスギノキミドリイシという枝状のサンゴです。
冬の低水温によるダメージも関係しているのか例年よりも1ヶ月ほど遅く、産卵の規模もやや小規模でした。
今のところ、その他の種では産卵が確認できていませんが、今後もぼちぼち観察を続けていこうと思います。
byひらりん
第250回 メス多くないですか?
当館にはウツボ類とその体を掃除するエビを展示した水槽があります。
そこで大きなウツボ類をせっせと掃除しているのが
こちらのアカシマシラヒゲエビ。
水槽のウツボ達もこのエビが掃除屋だということをよくわかっているようで
決して食べたりいじめたりしません。
さて、先日の閉館後、気持ちよさそうに掃除をされているウツボ達をボーっと眺めているとあることに気が付きました。
それは・・・
メス多くないですか?

というのも
水槽にいる10匹のエビのうちじつに9匹が抱卵していたのです。
ということは・・・
オス1匹×メス9匹の超ハーレム?
だとすると、なんとか時代のどっかの王様か!
甲殻類のなかには未受精卵を抱えるものもいるため9匹が抱えている卵の全てが受精卵とは限りません。
にしても超ハーレムには違いないはず。
よりどりみどりってか。
で、何となく気になったので調べてみました。
いくつかの文献をあたってみると、アカシマシラヒゲエビは雄性先熟の同時的雌雄同体だそうです。
つまり、小さいうちは全てオスですが、ある程度大きくなったらもしくはある年齢になったらメスに性転換するらしく、
さらに、形態的にメスになったあとも体の中で精子と卵を同時に作ることができるため、メス同士がペアになって精子を交換し合うことでお互いが受精卵を産むことができるそうなのです。
なにこのエビめちゃくちゃ面白い!!
さらに、アカシマシラヒゲエビが通常ペアで生活していることから考えると、
水槽内でもメス同士で繁殖しているものと思われます。
そこで気になるのは、唯一抱卵していない個体。
ぶっちゃけ、いまオスなのかメスなのかは形態を詳しく見ないとわりませんが
(勝手にオス設定でハーレムとか言ってすみません。。)、
はじめはみんなほとんど同サイズだったのになんか他個体よりも小さい気がする。
さらに何となく他の個体からいじめられているような気がする。
なんでかな~って見ていると、
なんと!
エビヤドリムシが寄生していました。

エビヤドリムシは寄生した宿主の生殖機能を阻害することが知られているようで、実際、寄生されたことで繁殖能力を失ったと思われる例が観察されているようです。
エビヤドリムシの寄生が宿主の性転換に及ぼす影響についてどこまで知られているのかは調べていないので分かりませんが、もし性転換を阻害する等の影響があれば非常に興味深いです。
少なくとも、今回唯一抱卵していなかった個体は生殖機能を失っている可能性がありますね。
(勝手にハーレムとか言ってすみません。。)
つまり
繁殖できない=ペアになれない可能性がある=他個体から拒絶される。
なるほど。(勝手にハーレムとか言ってすみません。。。)
ということで
現在、水槽内で繁殖可能な個体は全部で9個体。
これをペアにしていくと・・・4ペア+1個体・・・。
でも実際は9個体全て抱卵している=・・・
!!!
はい。
はじめハーレムの主のように見えた個体は実はとてもかわいそうな運命を背負っていて、
それにより残された9匹のなかではどこかで三角関係が勃発しているということになります。
はたして9匹はどうなるのか。そして残された1匹の運命やいかに。
今後の展開が気になります。
昼ドラか!!
by ひらりん