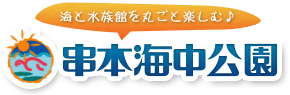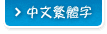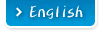スタッフブログ【さびうらびより】ブログ更新一覧
スタッフブログ【さびうらびより】ブログ更新一覧
スタッフブログ【さびうらびより】スタッフ:ブログ更新一覧
串本の様子や様々な串本の生き物たちを、
スタッフが交代でご紹介します。
- 最新記事
- 第394回 究極の8体
- 第393回 リアル夜の水族館
- 第392回 ウミガメの産卵始まりました
- 第391回 アオリイカの卵
- 第390回 ついにやってきた季節
- カテゴリ
- BigWest (6)
- Go (20)
- くろすけ♀ (71)
- くろちゃん (3)
- こて (18)
- さく太郎 (20)
- しまっち (25)
- そらすずめ (9)
- とーる (73)
- ひらりん (23)
- ひろぽん (6)
- ひーちゃん (12)
- まつ (5)
- ゆーみん (18)
- クチヒゲノムラガニ (5)
- ナツメリ (7)
- ハムいち (61)
- ブログ更新 (389)
- マンジュウイシ (1)
- 海人 (6)
- 青ネギ (4)
- 月別アーカイブ
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (9)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (5)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (2)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (3)
- 2012年1月 (3)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (3)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (5)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (6)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (5)
- 2010年4月 (4)
- 2010年3月 (3)
- 2010年2月 (3)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (6)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (8)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (7)
- 2009年6月 (5)
第394回 究極の8体
皆様は「スカベンジャー」という言葉を知ってますか?
漫画のタイトルなどになってたりもするようなので
他で聞いたことある方もいらっしゃると思いますが
私の今言ってるのは生物の話で
いわゆる「腐肉食動物」のことを指しております。
一言で説明すると他の生物の遺体などを食べる生物のことで
陸上生物だとハイエナやハゲワシ、ハエなどもこれにあたります。
当然、スカベンジャーは水中にもいて
色々な生き物が日々、死体の分解に勤しんでおります。
今日、紹介したいのはこちら。

ムシロガイです。
ムシロガイは北海道以外の日本各地に広く分布しており
水深20mより浅い海に生息する貝の仲間です。
このムシロガイの仲間もスカベンジャーとして知られています。

普段は半分ぐらい潜った状態で
水管を砂の上に出していますが
餌の匂いをかぎつけると砂から出てきて食べ始めます。
現在、館内の生物多様性水槽コーナーにて展示中なのですが
餌を食べるムシロガイのタイムラプス動画で撮影してみました。
その模様をどうぞ。
結構な勢いで食べてくれます。
食事自体は大体30分ぐらいで
満腹になったであろうムシロガイはまた砂の中に戻っていきます。
肝心の餌の方は

身の表面はほぼこそげ取られており
ぺらっぺらです。
一晩置いといたらもっと骨だけになっていることでしょう。
「生き物の死体を食べるなんて・・・」と思う方もいるでしょうが
このような生物たちがいてくれるおかげで死体が分解され
再び食物連鎖の輪の中に戻って来るわけです。
自然界においてスカベンジャーたちはなくてはならない存在です。
確かに華はないかもしれませんが
このように地味でも世の役に立つような存在
サウイフモノニワタシハナリタイ
by ハムいち@るろけんもぶそれんも大好き
第393回 リアル夜の水族館
梅雨に入り、一気に蒸し暑さが押し寄せてきました。
くろすけ♀です。
涼をもとめて水族館に来られる人も
多いかと思います。
そこで、もっと涼しい気持ちになっていただこうと
夜の水族館を紹介します。
照明の色を夜っぽくして、
夜の水族館と称して、お客様に見ていただくところもありますが
このブログでは、当館のリアルな夜の水族館を紹介します。
まずはエントランスから。

昔、ハムいち氏も言っていましたが
昼間は何とも思わない写真のダイバーが
夜になると不気味です。
さらに、消火栓の赤いランプが、一層雰囲気を作り出しています。
続いて玄関水槽から大水槽


真っ暗で中の魚は見えませんね。
暗い水槽に懐中電灯を向けると
魚が驚いてパニックになり
壁やサンゴにぶつかることがあるので
できる限りライトを使わず進みます。
続いてウツボの水槽。
ウツボは夜行性なので、
夜の方が姿をよく見せてくれます。
今夜もウツボが元気に泳ぎまわっていました。

クラゲのところにくるとホッとします。

そして、実物大アーケロン。

暗闇に浮かぶアーケロン。
なかなかの迫力です。
小さいときの私ならあまりの恐怖に
泣き叫んだかもしれません。

ウミガメコーナーからは外の風景が見えるのですが
私はいまだにここが少し怖い。
ガラスの向こうに誰かがいそうな気がするのです。
そして、終点トンネル水槽。


ここはいつも空気がひんやりしています。
そして、ミシッとかパキッとかいう音が
常に聞こえます。
リアル夜の水族館、いかがでしょうか。
涼しくなっていただけましたか。
フラッシュをたかずに写真を撮ったので
暗い写真ばかりですが、本当の夜の水族館を
味わっていただけたかと思います。
因みに変なものが写っていたとしても
報告は必要ありません。
宿直の夜は、毎晩このコースを見回り
眠りにつきます。
今夜も何事も起きないよう祈りながら…
飼育員にとって、お化けよりも
夜の警報が一番肝が冷えるのです。
by くろすけ♀
第392回 ウミガメの産卵始まりました
今年もウミガメ産卵の季節になりました。
早速、6月4日にアカウミガメの今年第1号産卵を確認しました。
ウミガメ担当である私は、6月から7月末までの産卵期間中は産卵チェックのためほとんどの日は
24時頃まで水族館に残って観察しています。
そこで問題となるのは夕食です。
弁当を作るほどの料理スキルややる気はないですが、毎食弁当を買っていたら食費が大変なことに
なってしまうので水族館で夕食を作っています。
職場にキッチンや冷蔵庫などはあるので調理ができますが、流石にがっつり料理をするのも大変
なので基本そばかうどんを茹でて食べています。
そんなわけでこの時期の夕食は、およそ週5でそばかうどんを食べています。
ちなみにそばとうどんを交互ではなく、
そばそばそばそばそばその他その他うどんうどんうどんうどんうどんその他その他
です。
そばとうどんは好きなので意外と平気です。
また今年もウミガメの産卵・孵化脱出ライブ配信は行う予定ですが、現在バタバタしていてまだ準備が
終わっていません。
近日中に配信を開始する予定ですのでもう少々お待ちください。
by とーる
第391回 アオリイカの卵
皆さんこんにちは!!
春ももう少しで終わりの時期になりましたね。
気が付いたら私も串本に来て1年が過ぎてました・・・
まだまだ実力不足を痛感する日々・・・
水族館に来られる皆さんに喜んでいただける展示を目指してこれからも頑張ります!!
さて、今回はそんな私の担当する水槽の紹介をさせていただきます!
こちらは軟体動物を展示する水槽で展示中のアオリイカの卵です。
5月8日に搬入されました当時の写真です。見た目や大きさはまるで白いエンドウ豆のようです。
この1つのフサの中に5~7個程度の卵が入っています。
そこから2週間ほどすると中の卵がかなり大きくなり、くびれができます。
個人的にはエンドウ豆から枝豆に変化したような感じだと思ってます!!
数日前に中身を取り出し撮影した物です。
一番左側の大きな丸い部分には卵の中で成長するのに必要な栄養が入っており、
それをほとんど全て吸収してから孵化します。
その右側には短い足が確認でき、さらに右側の赤い部分は目です。
現在展示中の卵もよくよく見てもらうとこの小さな小さなイカさんを観察することができます!!
卵を保護する卵嚢に包まれているため少し見にくいですが、是非是非ご覧下さい!!
あと1~2週間ほどしたら孵化するかな???
byまつ
第390回 ついにやってきた季節
暖かくなってきました。
ヒートテックをいつまで着るか、悩んでいるさく太郎です。
わたしのブログではわりと毎回言っている気がしますが、一番好きな季節、春の訪れです。
生き物たちが寒い冬を乗り越え、一斉に動き出す春がとても好きです。桜も好きです。桜味のお菓子はあまり好きではないです。

こちらはサツキハゼです。
真っ白なお腹がぷっくりと膨らんでいます。お腹の中に卵を持っています。
5月辺りが繁殖期です。

イソヒヨドリの雛
水族館の屋上で飛ぶ練習をしていました。冬に親鳥が、暖かいバックヤードに入ってくることがありましたが、
子育ての準備をしていたのでしょうか。
少し驚かせてしまって、ゲゲッと言っているかのような表情になっています。ゴメンネ
そして私の中では毎年恒例、カエル探しの解禁季節でもあります。

ぽっちゃりお腹のニホンヒキガエル
恐らくメスです。この内側に向いている前脚が可愛いんですよね。土下座しているみたいで。

カジカガエル(恐らくメス)
夜渓流付近で耳を澄ますと、ヒョロロロと高めの美しい鳴き声が聞こえてきます。
都会では中々お目にかかれません。かわいい。

オタマジャクシ(恐らくヤマアカガエル)
カエルの中でも産卵シーズンが早いです。2月あたりから繁殖期に入るそうで、これは4月初めの様子です。

こちらは一ヶ月後の様子
もう変態して、上陸していました!!The・ヤマアカガエルの見た目をしています!

大きさで言うとこんな感じ
気が付かないと踏みつぶしてしまいそうで、恐る恐る、忍び足で観察していました。

この個体は完全に稚ガエルの姿になっています。
オタマジャクシの頃の尻尾は脚が生えても一定期間残っていますが、徐々に体に吸収されていきます。
がわいいッ!!!!!
相変わらず魚よりカエルが多くなってしまいましたが、春はいい季節と言うことですね。
水槽内でも、あちこちで春の訪れをご覧になることがあるかも知れません。
ぜひ、生き物たちとの四季を体感していただきたいです。
by さく太郎