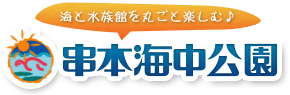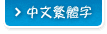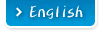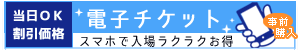スタッフブログ【さびうらびより】ひらりん一覧
スタッフブログ【さびうらびより】ひらりん一覧
スタッフブログ【さびうらびより】スタッフ:ひらりん一覧
串本の様子や様々な串本の生き物たちを、
スタッフが交代でご紹介します。
- 最新記事
- 第360回 錆浦より
- 第353回 さんごガチャふぁいなる
- 第347回 さんごガチャ中間報告
- 第342回 目目連
- 第337回 石の上にも四年
- カテゴリ
- BigWest (3)
- Go (20)
- くろすけ♀ (67)
- くろちゃん (3)
- こて (18)
- さく太郎 (16)
- しまっち (25)
- そらすずめ (9)
- とーる (69)
- ひらりん (23)
- ひろぽん (6)
- ひーちゃん (12)
- まつ (1)
- ゆーみん (18)
- クチヒゲノムラガニ (5)
- ナツメリ (7)
- ハムいち (57)
- ブログ更新 (366)
- マンジュウイシ (1)
- 海人 (6)
- 青ネギ (4)
- 月別アーカイブ
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (9)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (5)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (2)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (3)
- 2012年1月 (3)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (3)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (5)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (6)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (5)
- 2010年4月 (4)
- 2010年3月 (3)
- 2010年2月 (3)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (6)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (8)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (7)
- 2009年6月 (5)
第360回 錆浦より
黒潮の大蛇行が始まってからもうすぐ5年になろうとしています。
2017年夏、黒潮の大蛇行が発生したというニュースを見ていた時には想像していませんでしたが、その冬に発生した記録的な低水温現象は錆浦の海に深い爪痕を残すものとなりました。
浅場のイシサンゴ類は凍死したものや感染症に罹患したものがあふれ、
海底には凍死したウニやナマコの死骸が転がり、
水面を見上げると凍死した魚類が浮いていました。
海中では穴の中で凍死したワモンダコや瀕死のクマノミなどが散見され、自分の今いる場所が本当に錆浦なのかを疑いたくなるような光景は今でも鮮明に脳裏に焼き付いています。
この低水温現象をもたらしたのは黒潮の蛇行、冬の大潮干潮、そして列島を襲った記録的な大寒波でした。
それから4年後、幸いにも安定した水温に恵まれて見違えるように美しく回復した錆浦の海を以前もこちらのブログでご紹介しました。
しかし、
本年1月24日―25日にかけて、今度は過去最強クラスの大寒波が同じく列島を襲いました。
ここ串本にも雪が積もり、25日の朝には私が串本に来てからの8年間で見たこともない白銀の光景が広がりました。


当日は大潮後の中潮でまずまず潮が引くうえ、最干潮が午前2時頃ということで再びイシサンゴ類に大きな被害が出たのではないかと心配していましたが、
幸いにも大きな被害はなかったようです。
全体の5%ほど低水温により凍死した群体が散見されましたが、
これは例年に比べてやや多い程度であり、顕著な白化もなく、どうやらサンゴ群落のほとんどは今回の大寒波を乗り越えてくれたようです。
海中公園2号地区には相変わらず、息をのむような美しい水中景観が広がっていました。
一度は壊滅的な被害を受けたスギノキミドリイシも順調な回復をみせています!
環境は変動的であるため、生物の組成や今ある景観が同じであり続けるということはとても難しいことです。ここ錆浦の海も、これからさらに長い時間をかけ、良くも悪くもその海中景観を変化させていくことでしょう。
ただ、錆浦を信愛する一人のファンとしては、
この多様性あふれる豊かな海が少しでも長く、変わらない美しさであり続けることを祈っています!
これからも素敵な錆浦でありますよーに!!
おしまい。
by. ひらりん
第353回 さんごガチャふぁいなる
前回の私のブログではさんごガチャ中間報告ということでサンゴの子供達を紹介しました。
今回は一部、水槽デビューした子達を紹介します。
その後
夏の高水温にも耐え、
すくすくと成長した1歳のサンゴ達、
その一部が9月下旬についに水槽デビューしました。
たくさんある内の3群体だけですが、
正真正銘、2021年8月1日に錆浦で生まれた我が子達です。
いや~ここまで長かった。。
自然海水を掛け流している当館では稚サンゴを飼育しているシャーレに海藻や石灰藻が生えまくるので、時間を見つけては歯ブラシやピンセットでサンゴの周りの海藻を掃除し、
小さなうちはヨコエビやウミケムシなどに囓られるのでそうした小さな生物もこまめに取り除き、
餌の日にはピンセットの先を使って1群体ずつ魚とエビのミンチを与えたりしながら1年間育ててきました。
そのおかげもあってか、
今ではポリプはむっちむち。
褐虫藻はばっつんばっつんです。
大きさは最大の物で現在3~4cmくらいですが、
水槽内の環境も良く合っているようで、移植してからまた一回り大きくなったような気がします。
未だ種類ははっきりしませんが、
このまま大きくなってくれればいずれ分かることでしょう。
とりあえず今は、子供達の健康とさらなる成長を祈るばかりです。
ちなみにこの子達は水族館Aゾーン、「サンゴ・イソギンチャクの仲間コーナー」のでっかいウミバラのいる水槽に展示しています。水槽正面の目立つ場所に移植されていますので、当館に来る度に大きくなる(であろう)この子達の様子を是非とも見守って頂ければ幸いです。
メデタシメデタシ。
by. ひらりん
第347回 さんごガチャ中間報告
さかのぼること20回前の当ブログ
「さんごガチャ」的な感じでサンゴのスリックを育てていますという報告をしたのは私です。
そんな記事がこの世に存在したこと自体、記憶しているのは全人類の中で私1人だと思います
が、
つづけていましたとも。。人知れず
せわしていましたとも。。一生懸命
な~んてね。。ウへへ。
で、
ブログの順番がまわってきたもののとくにネタもないので
せっかくだから中間報告します。
まずは全体像から。
2021年8月。育て始めてしばらく経ったものがこちら。このころはまだプラヌラ(幼生)のものも居たような気がします。
で、現在の様子がこちら。シャーレは汚れていますが、サンゴの存在が視認できます。
では肝心のサンゴ達はといいますと
2021年8月時点では着底間もない稚サンゴが小さな骨格を形成していましたが、
今はサンゴらしくなり色もついてきました。ちゃいろくて褐虫藻がいっぱい。ウフフ。
ほかにも
タバネサンゴ?的な子がいたり
キクメイシ?Micromussa?なんだこれは?的な子達がいたり
もはやなんじゃこりゃ?的なラブリーな子がいたり。ニヤリ。
個性豊かな面々が着々と育ってきております。
因みにサイズ的にはこんな感じ。
群体(もしくはまだ個体の)サイズは概ね5mm~25mmといったところでしょうか。
ミドリイシの仲間だともう少し成長も早いようですが、
今回はすべてそれ以外。
ほぼ丸1年育てても小さいものは未だ5 mm程度ということで
種名が分かるまで、まだまだ先は長そうですね。。
これからも細々と世話を続けていこうと思います。
終わりに。
そんな私の気持ちを知ってか知らずか
今日も呑気にびょ~~んと伸びていたり、
肉部がモコモコだったりする、そこの我が子達よ!
父さん、今日はおまえたちに伝えたいことがあります。
これからも
たくさん食べて、燦々と光を浴び、いつか、でっかい大人になるんだぞ。
以上。
by ひらりん
第342回 目目連
目目連(もくもくれん)
鳥山石燕の画集「古今百鬼拾遺」にある日本の妖怪。家の障子に無数の目が浮かび上がるというもの。
出典:フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」より。
風も徐々に温みはじめた春の夜中
やや湿気味を帯びた風が
まるですすり泣くかのように時折肌をなでる
そんなある日の夜
誰もいない水族館で一人の飼育員が目撃した
なんとも奇怪なものがたり.....
・・・・
当館には毒棘を持つ魚としてゴンズイを展示するやや大きめの水槽があるのですが、
直射日光が当たらない水槽のため、その壁は付着物が少なくゴツゴツとした岩肌のような景観となっています。
この水槽では20cmほどもあるゴンズイ達が大きなゴンズイ玉を作って泳ぎ回る様子をご覧頂けるほか、隠れキャラとしてカノコイセエビや小さなオイランヤドカリなんかも入っています。
このゴンズイ達、ずいぶんと小さな頃から飼育していますが、
最近、朝一番は水槽底の右端でぐで~んとしており、なんだか「まだ寝たい。。」といっているようなやる気無い感じが観察できます。
しかし・・・
私は見てしまった。
そんな平和な水槽の中にいたのは彼らだけでは無かったのです。
ある宿直の夜22時をまわった頃。
不意にゴンズイの水槽を照らした私は思わず足を止めました。
そこにはなんと水槽の壁を動き回る無数の光る目が私を見つめていたのでした・・・。。
おわり。
というわけで、この水槽、じつはたくさんの小さなゾウリエビも入っていたわけです!
その数15匹!
最初は残った餌なんかを食べてもらおうと入れてみたのですが、
昼間、壁に擬態する姿があまりに巧妙で面白かったため、こっそり展示個体を増やしていったのでした!
その結果、
昼間はまるで何もいないように見えるのですが、夜になると無数のゾウリエビが壁を動き回っている水槽になってしまったわけです。じつは最初の画像にもゾウリエビが写っていたりします。
残念ながら夜の水槽はご覧頂けませんが、宿直の夜など水槽を照らすと、ライトの光を反射したゾウリエビの目がたくさん光っていて、まるで障子に写る目目連のようです。
あまりに巧妙な擬態ゆえ、開館中にこの水槽のゾウリエビに気づいた方は少ないかと思いますが、機会がありましたら15匹すべての擬態を見破ってみてはいかがでしょうか!(※飼育員の気まぐれでもう少し数が増える場合もございます)
(例題)下の写真、みなさんはどこにゾウリエビがいるか分かりますか???(見破りレベル:初級)
以下:答え
おまけ。
因みに、朝はやる気の無いゴンズイ達ですが、餌の時間はやる気全開です。
ゴンズイ達の「ヒャッハーー!」という声(想像)を脳内再生しながら以下の動画もご覧下さい。
メデタシメデタシ。
by ひらりん
第337回 石の上にも四年
遅くなりましたが、
皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年も変わらぬご愛顧の程何卒よろしくお願いいたします。
さて、新年初潜りということで先日、ダイビングパーク前にある串本海域公園2号地区にサンゴの調査に行ってきました。
ご覧の通り、このポイントは串本でも有数のすごく美しい水中景観で、
一面に広がるクシハダミドリイシ群落(写真:卓状サンゴ)とそこに群れる小型魚類に圧倒されるような、見ていて全く飽きない魅力があります。
それからこの地点は串本のサンゴの強さといいいますか、その生命力を目に見えて感じられる地点でもあります。
というのも、ここは2017年末から2018年初頭にかけて黒潮の大蛇行と記録的な寒波に伴う異常な低水温現象により、サンゴの大量斃死(凍死や弱ったサンゴ群落での感染症の蔓延による)が起こった場所なのです。
こちらが2018年1月の同じ地点の様子です。白く白化している部分はすべて低水温によって凍死したサンゴ群落になります。
こちらは別の角度から、白くなった斃死箇所と生きている箇所の境目が分かります。
それからこちらが2018年3月の同じ地点の画像です。
真ん中の濃い緑色の部分は既に死んだサンゴが藻で覆われており、その周りの部分もかろうじて生きてはいますが、低水温が続いたことによって色が薄くなり白く白化しています。その後、この白化した群体も大部分が斃死してしまいました。
こちらも2018年3月の画像。この群落はほとんどすべて斃死して藻に覆われています。
最終的に2018年初頭の低水温によって、ここ海域公園2号地区のイシサンゴ類は2m以浅の群落を中心に50%ほどが斃死してしまったのでした。
それから4年。
この地点のサンゴ群落がどうなったかというと・・・
・・・
・・・
・・・!
幸い、その後は冬季の顕著な低水温現象は起こらず、
2020年には夏場の高水温による大規模な白化現象が発生したものの、大きな斃死被害には至らずといったわけで、たった4年でこんなにもめざましい回復が確認されました!
環境が整えばサンゴは強い生き物だと言いますが、まさにその言葉を体現してくれているようですね。
串本では江戸時代ごろからサンゴの骨格を高温で蒸し焼きにして、漆喰の原料となる消石灰(熊野灰)を作る産業があったと言われており(現在その文化は無くなっていますが)、少なくとも1931年にはクシハダミドリイシを優占種としたサンゴ群落の存在が報告されています。
また、当館前に広がる海岸は串本の方言でサンゴを意味する「錆」という言葉からサンゴの多産する海域として「錆浦」の地名が付けられていることからも、串本にはかなり昔からサンゴが分布しており、当地の文化と密接に関係してきたことがうかがえます。
少なくとも約百年以上にわたる串本のサンゴの歴史の中で、おそらくこの海域公園2号地区のサンゴ群落はこれまで何度も危機的な状況を乗り越え、今ある美しい姿を形作ってきたのだと思います。
コロナ禍に伴う大変な状況が続く中ではありますが、我々もこのサンゴ群落のように今はじっと耐え、その後のめざましい回復に備えたいものですね!
新年早々、柄にも無く真面目な事を書いてしまいましたが、
願わくばこの美しいサンゴの海を長く見続けていけることを祈っています!
メデタシメデタシ。
by ひらりん