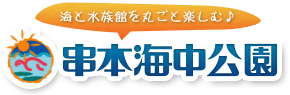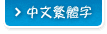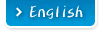スタッフブログ【さびうらびより】STAFF BLOG
串本の様子や様々な串本の生き物たちを、
スタッフが交代でご紹介します。
- 最新記事
- 第389回 月光に輝く「ゲッコウスズメダイ」
- 第388回 あなたが噛んだ水槽が痛い
- 第387回 だって魚だもの
- 第386回 ウミガメの交尾の季節となりました
- 第385回 アオイガイの展示
- カテゴリ
- BigWest (6)
- Go (20)
- くろすけ♀ (70)
- くろちゃん (3)
- こて (18)
- さく太郎 (19)
- しまっち (25)
- そらすずめ (9)
- とーる (72)
- ひらりん (23)
- ひろぽん (6)
- ひーちゃん (12)
- まつ (4)
- ゆーみん (18)
- クチヒゲノムラガニ (5)
- ナツメリ (7)
- ハムいち (60)
- ブログ更新 (384)
- マンジュウイシ (1)
- 海人 (6)
- 青ネギ (4)
- 月別アーカイブ
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (9)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (5)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (2)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (3)
- 2012年1月 (3)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (3)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (5)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (6)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (5)
- 2010年4月 (4)
- 2010年3月 (3)
- 2010年2月 (3)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (6)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (8)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (7)
- 2009年6月 (5)
第359回 大晦日の過ごし方は人それぞれ
あけましておめでとうございます!!!
2023年も串本海中公園をよろしくお願いします。
年を越して早2週間ほど経ちましたが、
私の大晦日の過ごし方について少し雑談を(たぶん誰も興味ない)...
2020年の大晦日をはじめに、私はなぜか右手にタモ網を持ち、夜な夜な魚類の採集をしています。
仕事納めならぬ、採集納めと界隈では言われているようです。
2020年の大晦日は高知県大月町で、2021年は沖縄県西表島で魚類の採集をしていました。
ちなみに、2020年と2021年は気づけば漁港で年を越していました。
ということで、2022年の大晦日もここ串本町でしっかりと採集納めをしてきました!
以下、採集納めの結果。
1種目 「ハナミノカサゴ」
毒棘に絶対的な自信があるのか、近づいても逃げる様子はなく採集は容易。
(※海で見かけても、触らずそっとしてあげてください。刺されないためにも)

2種目 「ツノダシ」
夜間は寝ているので比較的採集は容易。

3種目 「ニジギンポ」
同行者が採集。顎に大きな犬歯があり、噛まれると痛い。

そんなこんなで、コタツが恋しくなってきたので1時間ほどで撤収しました。
スーパーで年越しそばを買い、久しぶりに自宅で年を越しました。
ちなみに、2022年(去年)のベスト採集フィッシュ第一位は...
メガネモチノウオ(ナポレオンフィッシュ)の幼魚です。

ベラ界のキングで、成魚は最大2mを超えるらしい。
最後に、ご挨拶が遅れましたが昨年11月より入社したBig Westと申します。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
by Big West
第358回 月が変わって新年よ!
というわけで
2022年ももう終わります。
個人的に今年一年の中で記憶に残っているのは
滋賀県に旅行に行ったことです。
琵琶湖のほとりの道の駅に到着して車から降りて
潮気でべたつかない風を浴びたときに
湖に来たんだなって実感したのはいい思い出です。
さて
毎年恒例のお正月水槽をやっております。

2023年の干支にちなんで
ウミウサギガイの展示を行っています。

ウミウサギガイはいわゆるソフトコーラルを食べるので
長期の展示となると餌の確保が難しかったりします。
しかし、今回は短期間と言うことで
普通に暮らしていたら中々見ることのないであろう本種を
展示しております。
ウミウサギガイの名前の由来は貝殻の色から来てると言います。

このつややかで真っ白な貝殻。
これ見てウサギってつけるってオシャレじゃん。
でも生きた個体だと外套膜という膜で貝殻を覆ってしまっているため
この状態で見ることができません。
でも
私的には外套膜を広げた姿にこそウミウサギガイの魅力があると思っております。

こちらがウミウサギガイの生体の写真です。
この黒い絵の具に黒を混ぜたような真っ黒。
そしてその上に星空のようにちりばめられている白い点。
これを美と言わないでなんと言うでしょう。
調査などで潜っているときに
ウミウサギガイがついていそうなソフトコーラルを見つけると
この美しさを見たくてついつい探してしまう程です。
そんなウミウサギガイを展示しているので
お時間ありましたら是非とも見に来て下さい。
1月15日までやってますよー。
by ハムいち@昔、飼ってたウサギの名はピーター
第357回 この冬一番の寒い朝
この冬一番の寒気がここ串本にも訪れています。
寒い朝が超苦手なくろすけ♀です。
朝起きられない。
冷え込んだ今朝、オープン前の水槽を見回っていたら
こんなのを発見しましたよ。
ゴンズイのやる気のない
押しくらまんじゅうです。(笑)
よく見ると、押し出されたヤツが
とりあえず中に入ろうとがんばってます。
魚って変温動物で、体温は周囲の水の温度と同じって
いうけど、マグロとか筋肉の多い魚は
体温が高いって言われています。
だから、「マグロを釣ったらすぐ氷水に入れんと
身が煮えてしまう」って、漁師さんからも
聞いたことがあります。
ゴンズイはどうか分かりませんが
やっぱり群れの中心は多少暖かいのでしょうか。
あの群れの中に手を入れたい衝動にかられます。
今度入れてみようかな~
ちなみに、ゴンズイには毒針があります。
よい子はマネをしないでください。
まあ、このゴンズイたちが、寒くて身を寄せ合ってた
かどうかは分かりません。
だって、だいたいいつもこんな風に集まっているから(^_^;)
押しくらまんじゅうと言えば、小学生の頃、寒い冬の日に
学校の運動場で、みんなで押しくらまんじゅうした記憶が
よみがえってきました。
あの頃、冬でも体操服は短パンはいてたな~とか。
子ども多かったよな~とか(昭和50年頃の話)。
令和になって早4年。
それも終わろうとしています。
皆さまお体にはくれぐれも気をつけて
よいお年をお迎えください。
by くろすけ♀

その前にクリスマスがあるよ~
第356回 飼育員は見た!クマノミ夫婦の危機?
「串本の海」水槽に、1組のクマノミのペアがいます。
年齢はよく分かりませんが、10年以上は飼育されています。
このクマノミペアはイボハタコイソギンチャクをすみ家にしていて、その周りを縄張りにしています。

去年の今頃は、同じ水槽にもう1組別のクマノミペアがいました。
こちらのクマノミは、先のクマノミから4mほど離れたところで、サンゴイソギンチャクをすみ家にして暮らしていました。

ですが、この夏オスが死んでしまい、もう1匹のメスも姿が見えなくなり、サンゴイソギンチャクは空き家になっていました。
最近になって、この空きサンゴイソギンチャクにイボハタゴイソギンチャクで暮らしていたメスのクマノミが来るようになりました。
そして、イボハタゴイソギンチャクにはオスのクマノミが1匹で過ごすことが多くなりました。

この状況は・・・熟年別居?
時々、メスが帰ってきていることもありますが、どことなくぎこちない感じが・・・

クマノミの世界にもいろいろ事情があるのでしょうか。
ただ、オスのクマノミは1匹で過ごしていると、メスに性転換していくように思うので、それはそれでややこしくなりそうです。
クマノミのメス同士のケンカは壮絶だから。
しばらくこのクマノミ夫婦から目が離せません。
by くろすけ♀
第355回 ウミガメの口の中
水族館で飼育しているウミガメたちは、餌をもらうことを段々覚えていきます。
長く飼育している個体は、人影が見えると餌を食べられると思って近づいて来て口を開けて要求してきます。
慣れるとくちばしを触って口を開けさせて、そこに餌を投げ入れて食べさせられるようになります。
ただし、口内をチェックするときには有用ですがそれ以外にはあまり意味はありません。
水槽に餌を投げ入れれば勝手に食べますしね。
動画に出てくるのは、若いアカウミガメと成体のアカウミガメです。
若いアカウミガメの方は体色が白っぽいですが、この個体は生まれつきの色素異常です。
餌が欲しくて口を大きく開けてくれるので、口内が良く見えます。
ウミガメにもちゃんと舌があるのが見えますね。
歯は、ウミガメには、と言うよりカメにはありません。
大昔、カメの祖先には歯があったようですが進化の過程で無くなってしまいました。
その代わりにくちばしが発達していてかなり強力です。
動画のアカウミガメは自然界ではカニや貝などを好物としており、硬い殻をくちばしで砕いて食べてしまいます。
ですので、ある程度大きくなったウミガメに嚙まれるとかなり危険で、指を千切られてもおかしくありません。
動画の様な餌やりは、慣れている飼育員だからですので一般の方はマネしないでください。
ちなみに私は、動画後半に出てくる様な成体のアカウミガメにがっつり指を嚙まれたことがあります。
作業中軍手越しに噛まれたのですが、あまりの痛さに指の感覚がなくなって軍手を取ったら指も一緒に取れるのではないかと思いました。
幸い無事でした。
小さいウミガメにはしょっちゅう噛まれるので、慣れてきて大分我慢できるようになりました。
もしくは、良い噛まれ方が分かるようになってきます。
by とーる