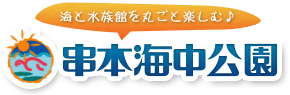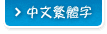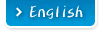スタッフブログ【さびうらびより】STAFF BLOG
串本の様子や様々な串本の生き物たちを、
スタッフが交代でご紹介します。
- 最新記事
- 第394回 究極の8体
- 第393回 リアル夜の水族館
- 第392回 ウミガメの産卵始まりました
- 第391回 アオリイカの卵
- 第390回 ついにやってきた季節
- カテゴリ
- BigWest (6)
- Go (20)
- くろすけ♀ (71)
- くろちゃん (3)
- こて (18)
- さく太郎 (20)
- しまっち (25)
- そらすずめ (9)
- とーる (73)
- ひらりん (23)
- ひろぽん (6)
- ひーちゃん (12)
- まつ (5)
- ゆーみん (18)
- クチヒゲノムラガニ (5)
- ナツメリ (7)
- ハムいち (61)
- ブログ更新 (389)
- マンジュウイシ (1)
- 海人 (6)
- 青ネギ (4)
- 月別アーカイブ
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (9)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (5)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (2)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (3)
- 2012年1月 (3)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (3)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (5)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (6)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (5)
- 2010年4月 (4)
- 2010年3月 (3)
- 2010年2月 (3)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (4)
- 2009年11月 (6)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (8)
- 2009年8月 (5)
- 2009年7月 (7)
- 2009年6月 (5)
題339回 船で調査
ブログネタが全然思いつかないので、やっつけで水族館の地味~なお仕事紹介
水族館の仕事の一つとして潜水環境調査があります。
調査自体そこそこ大変な作業ですが、報告書を書くのもかなりしんどいので、
報告書の時期には毎年うんうん唸りながら夜遅くまで文章を考えています。
また、調査地点まで行くのに船が必要なことが多いので、水族館の船をよく使います。
串本海中公園では船を3隻所有していて、
●半潜水型海中観光船「ステラマリス」
●ダイビング船「ネレイス」
●作業・調査船「オルカ6号」
があります。
そして飼育ではオルカ6号を使って、
潜水調査・潜水採集・釣り採集・ウミガメ放流・観測などを行っています。
これがオルカ6号で、小さめの漁船と言う感じです。
操船や管理は私の担当なのですが、個人的には操船の楽しさ<管理の大変さですね。
昨年末に行った串本町大島での調査の時の様子です。
12月なので寒かったですが、天候・海況は絶好でした。
調査前のダイバーです。
私は船長なのでお留守番です。
正直冬場の調査では留守番でほっとしています。
この日は潜水中のダイバーも上からよく見え、近くにキビナゴの群れも。
ここの水深は15m位だったと思います。
この時の様な状況だと、調査中私は船の上で特にやることが無くボケっとできて楽なのですが、
風が強い日や海が荒れているときは一転して、錨が外れて走錨しないか、暗礁にぶつからないか、
ダイバーの所在が分かり難い、船が揺れて酔う、とストレスMAXです。
by とーる
第338回 幸運のギョウザ
最近くしゃみが止まりません。目も痒いです。
花粉が来始めていませんかね。つらいです。さく太郎です。
今回も展望塔ネタです。仕方ありませんよね、見つかるんですものネタが。
展望塔で掃除をした帰り、ふらふらとしていたら、とても小さな水中に漂う物を見つけました。
はじめ見たとき、なにこれ!!紫色のクリオネ?!と思いましたが、手をそっとさしのべてみると、
ぴとっとくっつきました。
そこでウミウシだと気が付きましたが、初めて見る物にテンションがあがって水中で
わちゃわちゃしてしまい、最初動画を撮ることを忘れていました。
こちらは『ムラサキウミコチョウ』という、ウミウシの仲間で、水中を泳いで移動することがあります。
ウミウシの仲間の中には『ウミコチョウ科』の他にも水中を泳いで移動する種類もいますが、
特にこのウミコチョウ科はマンタのように、羽ばたいて泳ぐのが特徴です。
(実際に羽はなく側足と言うようですが。)

泳がないときはこんな風に、羽部分をたたんでいます。ギョウザみたい・・・
オレンジ色の突起がまたいいアクセントになっていてキレイですね。しかしとっても小さいのです。
宙に浮いていると、自分のタンクからでるエアーの泡ですぐに飛んで入ってしまうので、
ちゃんと動画で撮れている部分が短くなってしまいました。
だいたい体長は1~1.5cmくらいしか無く、普通に泳いでいたら気が付かない気がします。
運良く居場所を探して泳いでくれていたので、ラッキーでした!今年はついてる年になるのかも??
もう一匹ウミウシを見つけました。

こちらは『ミヤコウミウシ』です。(たぶん)
何だか毒々しさの中に美しさがあるというか・・・幻想的なウミウシですね。
有名な青い地の色に赤っぽい点々のある、アオウミウシはよく見かけますが、
こんな色のウミウシは初めて見ました。
ウミウシの仲間は3000種以上知られており、更に見つかっていない種が
まだまだいると言われているくらい、様々な形・色をした個体がいます。
今後岩の上なんかをよく見て、沢山の写真のコレクションを集めたいなと思います。
最近自前の水中カメラも購入したので!!
もう少し詳しくなったら、またブログに上げたいと思いますので、
ウミウシファンのみなさん、しばしお待ちを!
by さく太郎
第337回 石の上にも四年
遅くなりましたが、
皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年も変わらぬご愛顧の程何卒よろしくお願いいたします。
さて、新年初潜りということで先日、ダイビングパーク前にある串本海域公園2号地区にサンゴの調査に行ってきました。
ご覧の通り、このポイントは串本でも有数のすごく美しい水中景観で、
一面に広がるクシハダミドリイシ群落(写真:卓状サンゴ)とそこに群れる小型魚類に圧倒されるような、見ていて全く飽きない魅力があります。
それからこの地点は串本のサンゴの強さといいいますか、その生命力を目に見えて感じられる地点でもあります。
というのも、ここは2017年末から2018年初頭にかけて黒潮の大蛇行と記録的な寒波に伴う異常な低水温現象により、サンゴの大量斃死(凍死や弱ったサンゴ群落での感染症の蔓延による)が起こった場所なのです。
こちらが2018年1月の同じ地点の様子です。白く白化している部分はすべて低水温によって凍死したサンゴ群落になります。
こちらは別の角度から、白くなった斃死箇所と生きている箇所の境目が分かります。
それからこちらが2018年3月の同じ地点の画像です。
真ん中の濃い緑色の部分は既に死んだサンゴが藻で覆われており、その周りの部分もかろうじて生きてはいますが、低水温が続いたことによって色が薄くなり白く白化しています。その後、この白化した群体も大部分が斃死してしまいました。
こちらも2018年3月の画像。この群落はほとんどすべて斃死して藻に覆われています。
最終的に2018年初頭の低水温によって、ここ海域公園2号地区のイシサンゴ類は2m以浅の群落を中心に50%ほどが斃死してしまったのでした。
それから4年。
この地点のサンゴ群落がどうなったかというと・・・
・・・
・・・
・・・!
幸い、その後は冬季の顕著な低水温現象は起こらず、
2020年には夏場の高水温による大規模な白化現象が発生したものの、大きな斃死被害には至らずといったわけで、たった4年でこんなにもめざましい回復が確認されました!
環境が整えばサンゴは強い生き物だと言いますが、まさにその言葉を体現してくれているようですね。
串本では江戸時代ごろからサンゴの骨格を高温で蒸し焼きにして、漆喰の原料となる消石灰(熊野灰)を作る産業があったと言われており(現在その文化は無くなっていますが)、少なくとも1931年にはクシハダミドリイシを優占種としたサンゴ群落の存在が報告されています。
また、当館前に広がる海岸は串本の方言でサンゴを意味する「錆」という言葉からサンゴの多産する海域として「錆浦」の地名が付けられていることからも、串本にはかなり昔からサンゴが分布しており、当地の文化と密接に関係してきたことがうかがえます。
少なくとも約百年以上にわたる串本のサンゴの歴史の中で、おそらくこの海域公園2号地区のサンゴ群落はこれまで何度も危機的な状況を乗り越え、今ある美しい姿を形作ってきたのだと思います。
コロナ禍に伴う大変な状況が続く中ではありますが、我々もこのサンゴ群落のように今はじっと耐え、その後のめざましい回復に備えたいものですね!
新年早々、柄にも無く真面目な事を書いてしまいましたが、
願わくばこの美しいサンゴの海を長く見続けていけることを祈っています!
メデタシメデタシ。
by ひらりん
第336回 「とら」が好き
年末ですね。
あっという間です。
年を重ねると一年が過ぎるのが早く感じるようになると言いますが
2021年の過ぎ去り方はすごかったですね。
2021年は恐らく9ヶ月しかなかったんじゃないでしょうか。
そんな訳で
年末年始恒例のお正月水槽を今年も展示しております。

飾り付けはいつも通りって感じなのですが
展示生物は来年の干支の寅にちなみまして
目玉はトラフナマコとなっております。
その他には
トラと同じしま模様を持った魚達ということで
ゴンズイ、カゴカキダイなどなどが入っております。
TOO SHY SHY BOY!的なゴンズイが隅っこにいってしまうため
若干のスカスカ感がありますが
近くで見ると意外といっぱい入ってます。
コロナ禍の終息にはもう少し時間がかかるでしょうが
感染拡大予防をして来られた際は
是非ともこの水槽を見て明るい気持ちになっていただけたら幸いです。
ってな感じで2021年も一年間ありがとうございました。
2022年もこのペースでまったりとやっていきますので

来年もよろしくお願いいたします
~うちの娘の激カワ写真を添えて~
by ハムいち
第335回 ある冬の午後
怒濤の10月、11月が過ぎて
今年も残り半月を切りました。
秋は、修学旅行の案内をしたり
調査であちこち潜りに行ったり、
生き物たちの世話はもちろん
毎日が慌ただしく過ぎて行きました。
水族館の魚たちは、相変わらずです。
ボイラーが入ったので
今年もおなじみの行列が
見られます。

暖かい水が出るところに集まる魚たち
モンガラカワハギは
石に寄りかかって
食後のまったりタイム
今年の1月にやってきた
トサカハギは
この頃好奇心旺盛で
写真を撮っていると
やたらと写りたがります

トサカハギ
今年で30年目になった
モンツキベラは、
そのうち尾びれが二股に分かれて
「猫又」ならぬ「ベラ又」になるのではと
期待しております。

飼育30年目のモンツキベラ
生き物を飼っていると
赤ちゃんは赤ちゃんで
もちろんかわいいけど
歳をとった生き物たちは
愛おしく感じます。
みんな長生きしてね。
by くろすけ♀